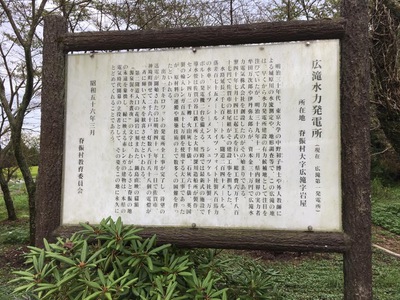2018年09月09日
2010年11月23日
森永煙草製造所跡



佐賀市・柳町界隈には煙草製造所が数軒ありました。その代表とされるのが、「森永煙草製造所」であり、ここで「富士の煙」が製造されました。
「富士の煙」は刻み煙草で、原料は鹿児島から有明海を渡り佐賀江を通って運ばれました。佐賀煙草が本格的になったのは江戸時代からですが、日露戦争のため明治37年に専売法が公布され民営の煙草製造は官営に移行し、「富士の煙」も製造中止となりました。
2010年11月15日
旧中村家



明治18年(1885年)に建てられた旧中村家は、旧古賀銀行の斜め向い、八坂神社の東隣に北を正面として建ち、古賀銀行が開業した際には、社屋として活用されたと云われます。
その後、明治39年に古賀銀行が新築移転した後は、中村家の住居として利用されてきました。
一部は、改築されていますがほぼ明治時代からの姿を残しており、柳町地区の歴史的景観を形成する貴重な建物です。
2010年08月29日
2010年08月28日
2010年08月27日
2010年08月17日
古賀精里の旧宅跡
古賀精里は、寛延2年(1749)佐賀郡西古賀村に生まれのちにここ、佐賀城下精小路に住みました。
江戸後期の儒学者で、名は撲、字は淳風、通称は弥助と云われました。陽明学を学び、のち江戸幕府の官学として保護された朱子学に転じます。
八代藩主・鍋島治茂により城下の松原小路にたてられた藩校「弘道館」の教授となり、弘道館の学則を制定しました。
寛政3年(1791)幕府の昌平黌の教官に抜てきされ、高松の柴野栗山、伊予の尾藤二州とともに寛政の三博士と呼ばれようになります。
精里は、号で住んだ土地にちなみ「精の里」を天下に発揚しました。
2010年08月16日
旧清力酒造株式会社・その2
この建物は、木造2階建ての洋風建築と和風平屋の倉庫部分から構成されています。
正面の玄関ポーチは、ヨーロッパの古典建築様式を用いた角材で組まれ、外壁は白一色にペンキが塗られています。
2010年08月15日
旧清力酒造株式会社・その1
旧清力酒造株式会社は、初代社長・中村綱次氏が明治41年(1908年)建てたものです。
建築にあたっては、中村綱次社長が大工を伴って長崎の洋風建築を視察し、設計の参考にしたと伝えられています。
現在は、大川市立清力美術館となっています。
2010年08月03日
旧唐津銀行本店
明治45年(1912年)建造の旧唐津銀行は、辰野金吾の弟子・田中実が設計しました。
保存が決まり、内装はすでに復元されています。外壁は赤タイルと白い石を張った赤煉瓦造りの建築構造で、辰野の影響を強く受けています。
2010年08月01日
2009年06月06日
軍艦島・その3
< 明治時代の軍艦島 >
端島では、1810年(文久7年)に石炭が発見され、佐賀藩が小規模な採炭を行っていましたが、1890年(明治23年)に三菱合資会社の経営となり、本格的海底炭鉱として操業が始まりました。
2009年06月05日
軍艦島・その2
< 昭和30年代の軍艦島 >
長崎半島から西に約4.5キロ沖合いに浮かぶ島、「端島(はしま)」。
海底炭鉱の島で、塀が島全体を囲い、高層アパートが立ち並ぶその外観が、軍艦「土佐」に似ているため「軍艦島」と呼ばれるようになりました。
2008年09月21日
2008年09月21日
高麗人の墓碑・逆修碑その1
佐賀市金立山の麓に、高麗帰化人の2基の石碑・逆修碑があります。この事は、山本常朝・口述の「葉隠聞書」第三にも記録が見られます。
逆修とは、生前にあらかじめ自分のために77日(49日)の仏事を修めて死後の冥福を祈ることで、これを記念して建てたものを逆修碑といいます。
2008年05月28日
初代・肥前国忠吉
佐賀市伊勢町・真覚寺には、「初代・肥前国忠吉」の墓がある。
初代忠吉は、元亀3年(1572年)高木村長瀬に生まれ、橋本新左衛門と称した。慶長元年(1596年)上京して、名工・埋忠明寿の門下となり刀工としての技を磨き、帰国後、現・長瀬町に居を移し、佐賀藩の抱刀工となった。
境内には、日本刀のさい焼きに使用した「水舟」や、「とぎ石」なども現存する。